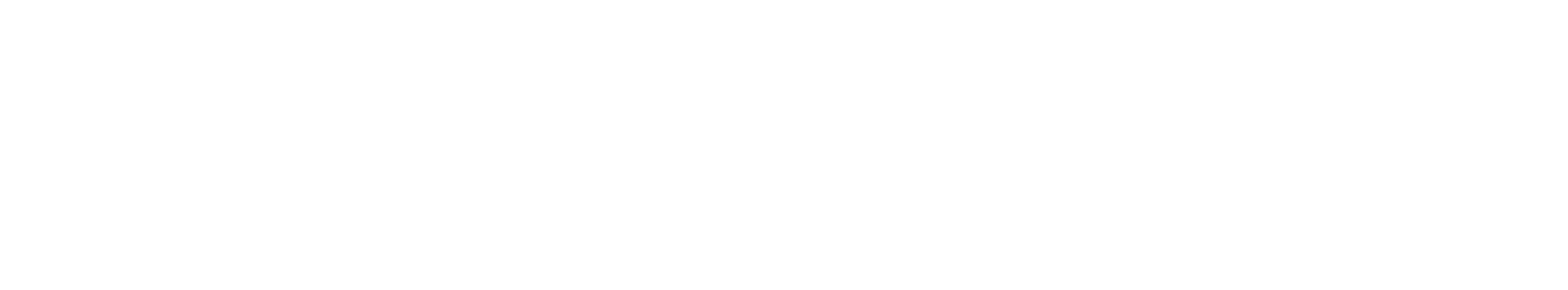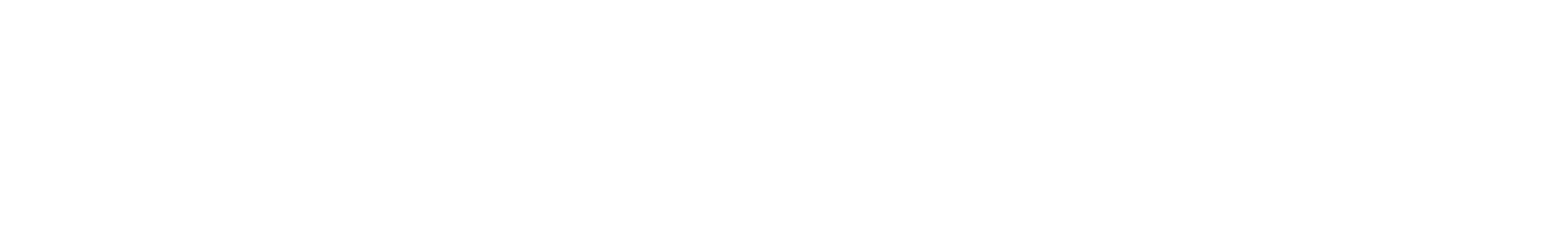楽焼筒茶碗_底
楽焼筒茶碗_底
Bottom View
| 19C中頃/江戸時代 | |
|
高(H)7.7 × 口径(WD)9.6 × 底径(BD)4.2 (cm) 刻銘「(花押)」共箱(蓋表)「赤茶椀/宝珠之画/澍露軒(花押)」、(側面貼札)「大正五年三月/赤小茶椀/宝珠之画」 |
|
| 滋賀県立陶芸の森陶芸館/The Museum of Contemporary Ceramic Art, The Shigaraki Ceramic Cultural Park | |
|
井伊直弼(II, Naosuke) 1815-1860/文化12-安政7 彦根城槻御殿 (現 滋賀県彦根市)生まれ |
開国派として日米修好通商条約に調印するなど、日本の開国・近代化を断行した幕末の大老。禅や国学また歌道を修めた当代一流の教養人で、石州流の茶の湯を学び一派を確立した大名茶人でもある。埋木舎時代から楽焼に手を染め、作陶に親しんだ直弼の積極的な関与のもと、彼の藩主時代に藩窯湖東焼は黄金期を迎えた。窯・製造場の拡充整備、京焼・九谷焼・瀬戸焼からの良工の招聘など、品質向上と生産体制の強化が進められている。 |
|
「楽焼筒茶碗」 |
井伊直弼が自作したという胴部に大小の宝珠を描いた茶碗。彼の自作茶陶に関しては、井伊家伝来史料『楽焼覚書』に記録されている26件の茶碗のひとつで、「-川比/筒茶碗/宝珠手」と推定されるもの。やや深めの筒型で高台は小さく、胴部は口縁に向けて僅かに広がり、内側に丸くすぼまる利休好みの形や丁寧な箆削りの仕上げに井伊家伝来品との共通した作風が認められ、また高台内の花押や共箱の箱書も同様に直弼自筆と確認できる。 |